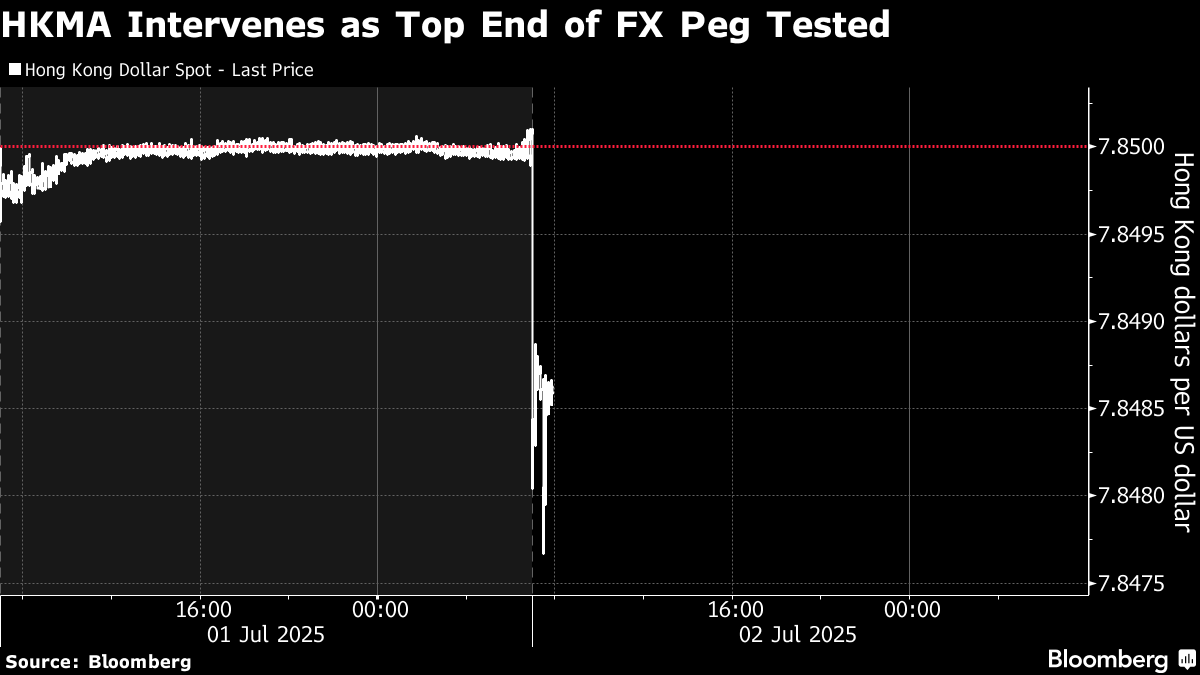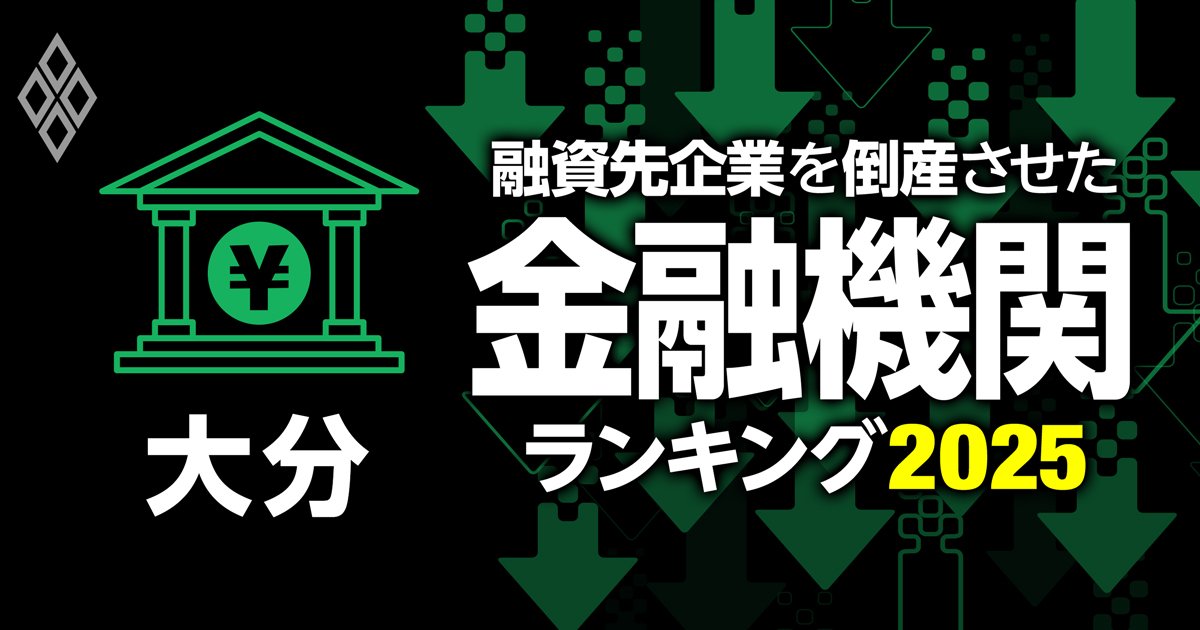サステナ情報開示義務化、中小プライム企業は対象外に? 金融庁の判断に背景

金融庁が、2027年3月期から始まるサステナビリティ(持続可能性)情報開示について、重要な方針転換を行うことが明らかになりました。当初予定されていた全プライム上場企業への義務化が見送られ、時価総額が一定額未満の企業は対象外となる方向で調整が進んでいます。
この決定の背景には、欧州連合(EU)をはじめとする海外市場での動向があります。EUでは、サステナ情報開示の対象企業を見直す動きが活発化しており、日本もその影響を受けています。特に、国内の東証プライム上場企業の中には、時価総額が5000億円未満で、海外投資家の割合が低い企業が多く存在します。
金融庁は、このような企業に対して、サステナ情報開示を義務化した場合、過剰な負担となる可能性があると判断しました。情報開示には多大なコストと労力がかかり、中小企業にとっては経営資源を圧迫する要因となりかねません。そのため、企業規模に応じた柔軟な対応が必要であるという考えに至ったのです。
今回の決定は、金融審議会(首相の諮問機関)の作業部会で近くまとめる「中間論点整理」の中で正式に決定される予定です。この中間論点整理では、時価総額5000億円未満のプライム企業が対象外となることが盛り込まれる見込みです。
しかし、今回の見送りは、サステナビリティへの取り組みを後退させるものではありません。金融庁は、中小企業に対しても、自発的な情報開示を促すための支援策を検討しています。例えば、開示の基準やガイドラインを整備したり、情報開示の専門家を派遣したりするなどの施策が考えられます。
サステナビリティへの関心は、世界的に高まっています。投資家は、企業のサステナビリティへの取り組みを重視するようになり、その情報を投資判断の参考にしています。今後は、企業が自発的にサステナビリティ情報を開示し、透明性を高めることが、企業の競争力を高める上で重要になってくるでしょう。
金融庁の今回の判断は、中小企業にとっては負担軽減につながる一方、サステナビリティへの取り組みをさらに加速させるきっかけとなるかもしれません。企業は、自社の状況に合わせて、最適な情報開示の方法を模索していく必要があるでしょう。